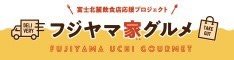富士吉田市のある山梨県は、日本のワイン生産発祥の地です。
歴史は古く、明治初期からワインの生産が始まったと言われており、今では山梨県内に国内の3割にあたる約100社のワイナリーがあります。
代表的な品種として甲州ブドウが知られており、その他にもマスカット・ベーリーAなど様々な品種が栽培されています。
そんな山梨県で作られる日本ワインと一緒に今回紹介したいのが、富士吉田市に深く根付いている馬肉文化、中でもたくさんの精肉店で扱われている馬刺しです。
かつては多くの馬が富士登山の際に荷運びを担っており、その役目を終えた馬の命を最後まで大切にするという考え方から、馬肉文化が根付いていったと言われています。
高タンパク低カロリーな馬刺しは栄養も豊富で、健康志向への傾倒と共に近年は人気が高まっています。
そんな馬刺しに合わせるお酒として思い浮ぶのは地酒・日本酒が一般的かと思いますが、日本で一番多くワインが作られている山梨県だからこそ地元の通は「馬刺し」と「日本ワイン」を一緒に楽しんでいるそうです。
キャンプなどで夜の宴を楽しみたい方にも、お土産としてちょっと気の利いたプレゼントを贈りたい人にも、いろんな人に楽しんで欲しい組み合わせになっています。
精肉店がおすすめする馬刺しを楽しむための「食べ方・薬味」についても紹介していますので、是非自分の好みのお店や食べ方、種類を見つけてみてください。
この特集では、山梨県産の日本ワインを購入できる酒屋3軒と、馬刺しを購入できる精肉店4軒を紹介します。
各店舗を効率よく巡るモデルコースについては、 「山梨県産ワイン×馬刺しの深い世界!酒屋・精肉店巡りで始める大人旅(半日)」 をご覧ください。
※価格については、変動することから掲載を行なっていません。また、在庫についても変動があるため、来店前に電話などでご確認いただくことをおすすめします。
やまいち LIQUOR STORE
山梨県産のワインはもちろん、海外のワインも豊富に取り揃えているやまいち LIQUOR STORE。
温度管理されたワインの販売スペースには、所狭しと様々な種類のワインが並べられています。
特徴的なのは、ナチュラルワインを豊富に取り扱っている点で、その割合は全体の8割ほどになるそうです。
店主の宮下さんに伺ったところ、ワインの販売を始めて間もない頃、ワインを飲んで二日酔いになったり、体調を悪くしたりという経験があり悩んでいたそうです。
そんな時、ナチュラルワインを飲んでみたところ、二日酔いにもならず、体調を崩すこともなかったことからナチュラルワインに興味を持ち、取扱量も増えていったとのことでした。
近年では、地元の方のみならず、他県からの来客も多くなっているそうです。
馬刺しにおすすめのワイン
紫藝醸造の「翠翠 赤 2024」をすすめていただきました。
マスカット・ベーリーAを主体に、カベルネ・フラン、トゥルソー少量といった品種を使った自然発酵亜硫酸添加なしノンフィルターで作られるナチュラルワインです。
地酒のモトヘイ
店名の通り、地酒や焼酎のお店として知名度の高い地酒のモトヘイですが、山梨県産を中心にワインの品揃えも充実しているんです。
キャンプに出かける前に立ち寄る方から、飲食店を経営している方の仕入れまで、様々な用途で使うことのできるお店となっています。
馬刺しにおすすめのワイン
勝沼醸造の「アルガブランカ デンショウ オレンジワイン」をすすめていただきました。
日本固有の品種「甲州」に特化したワインとして知られる「アルガブランカ」シリーズのオレンジワインです。
店主の勝俣さんに伺ったところ、国内でも取り扱っている酒屋が少ないため、手に入りにくいワインなので、ぜひ試してみて欲しいとのことでした。
1937年創業のワイナリーが、山梨県の代表的な品種である「甲州」で作るオレンジワイン、気になりますよね。
虎屋リカー
観光客に人気の富士みち(本町通り)から程近い場所にある虎屋リカーは、大人の秘密基地のようなワクワクする酒屋です。
その理由は、メインの店舗とは別の場所にたくさんのワインが保管してある場所があるからです。
店長の奥脇さんは、知識の量もさることながら、ワインへの熱量がとても高く、お話を聞いているだけで時間を忘れてしまうほどです。
馬刺しにおすすめのワイン
7c | seven cedars winery(セブンシダーズワイナリー )の「KOSHU CUVÉE SW 2024」と錦城葡萄酒の「BLOUGE」をすすめていただきました。どちらも自信を持って馬刺しと合わせて欲しいワインということで、どちらのワインを紹介するかは一任していただいたのですが、せっかくなので両方とも紹介します。
7c | seven cedars winery(セブンシダーズワイナリー )の「KOSHU CUVÉE SW 2024」は、2人の栽培者のワインをブレンドして造られる、甲州種 100%の白ワインです。
名前の「SW」が栽培者を表しているとのことで、他にも「W」「SF」「S」と、全部で4種類が造られています。
錦城葡萄酒の「BLOUGE」は、勝沼産のカベルネ・ソーヴィニヨンと甲斐ノワールをブレンドして作られたロゼワインです。
ロゼワインならではの綺麗な色合いと、果実味を楽しむことのできる味わいが特徴です。
肉の大西
肉の大西で販売されている馬刺しの部位は「肩肉」で、噛みごたえがあり、徐々に味が染み出してくる印象でした。
外国産ですが「タテガミ」など複数の部位が販売されている他、お土産に便利な冷凍の商品も販売されています。
馬刺しを楽しむための「食べ方・薬味」
肉の大西では、馬刺しを購入した方に小袋入りの辛みそを提供しているそうで、醤油に辛みそを解いて食べるのがおすすめとのことです。
辛みそは商品としても販売している他、オリジナルの馬刺し醤油も販売されています。
お茶や肉店
お茶や肉店で販売されている馬刺しの部位は「ヒレ肉」「サーロイン」「上モモ肉」など複数で、「上モモ肉」はしっかりとした肉感で食べ応えがある印象でした。
馬刺しには「山梨県肥育」と書かれており、お店の方に伺ったところ、別の場所で生まれてから山梨県にやってきて育てられる馬もいるのだそうです。
馬刺しを楽しむための「食べ方・薬味」
お茶や肉店で教えていただいたおすすめの「食べ方・薬味」は、スライスした生の玉ねぎに醤油をかける食べ方です。
生姜やニンニクと比べると控えめな薬味で、馬刺し自体の旨みを感じることができました。
肉のいがらし
肉のいがらしで販売されている馬刺しの部位は「ヒレ肉」で、並と上の2種類を販売しています。
「上馬刺し」は、滑らかであっさりとしていて、魚のお刺身のような印象でした。
その時によって、使われているお肉の部位が違うとのことですが、上馬刺しに関してはヒレ肉とロース肉を使っていることが多いということです。
馬刺しを楽しむための「食べ方・薬味」
肉のいがらしで教えていただいたおすすめの「食べ方・薬味」は、ポン酢とおろしニンニクを合わせる食べ方です。
ポン酢の酸味とニンニクの辛味が、馬刺しの旨みを引き立ててくれます。
伊藤精肉店
伊藤精肉店で販売されている馬刺しの部位は「モモ肉」で、味わい・食感共にマイルドな印象でした。
馬肉は山梨県内北杜市などで育てられているものを仕入れているそうですが、近年では需要の高まりから供給不足が顕著になってきているとのことでした。
馬刺しを楽しむための「食べ方・薬味」
伊藤精肉店で教えていただいたおすすめの「食べ方・薬味」は、生姜と醤油をかける食べ方です。
マイルドな赤身の馬刺しと生姜醤油で、いくら食べても飽きのこない相性の良さでした。
おまけ・その1「ワインと馬刺しの組み合わせ」
今回、たくさんのお店に協力していただき、ワインや馬刺しの食べ方についておすすめを教えてもらったので、それぞれを組み合わせてワインと馬刺しの組み合わせとしてのおすすめを考えてみました。
好みによって感じ方は異なりますので、これを参考にお気に入りの組み合わせを見つけてみてください。



好みによって感じ方は異なりますので、これを参考にお気に入りの組み合わせを見つけてみてください。
肉の大西の馬刺し×勝沼醸造の「アルガブランカ デンショウ オレンジワイン」
お茶や肉店の馬刺し×錦城葡萄酒の「BLOUGE」
肉のいがらしの馬刺し×紫藝醸造の「翠翠 赤 2024」
伊藤精肉店の馬刺し×7c | seven cedars winery(セブンシダーズワイナリー )の「KOSHU CUVÉE SW 2024」
おまけ・その2「馬肉の小話」
いくつもお店を回る中で、たくさんのお話を伺わせていただきました。
その中でも、印象に残っている小話を、いくつか簡単にご紹介します。
その中でも、印象に残っている小話を、いくつか簡単にご紹介します。
- ・富士吉田市では馬肉がとても身近な存在で、ある家庭では親子丼も鶏肉ではなく馬肉で作っていたんだとか。
- ・山梨県産の馬刺しは赤身肉が基本で、脂の多い部位は主に外国産の馬から取ることができるんだとか。
- ・肥育方法が発達して一年を通して馬肉を楽しめるようになったことで、旬というのはあまりないんだとか。
- ・子供が熱を出した時は、馬肉をおでこに貼っていたことがあるんだとか。
- ・釣りやキャンプに来た県外のお客さんが、何キロも馬肉を買っていくことも珍しくないんだとか。
- ・生産量を急激に増やすことは難しいこともあり、昨今の需要の高まりから供給が追いついていないんだとか。